ottomanは少子高齢化と人口減少が進んでいる時代の中で、生活の質を向上し社会へ貢献し続ける為の努力を惜しみません。
そして、スタッフの一人ひとりがプロフェッショナルとして自覚を持ち、質の高いサービスを提供できる組織を目指しています。
プロフェッショナルであることの追求と成長を続け、社会に貢献する
ottomanは少子高齢化と人口減少が進んでいる時代の中で、生活の質を向上し社会へ貢献し続ける為の努力を惜しみません。
そして、スタッフの一人ひとりがプロフェッショナルとして自覚を持ち、質の高いサービスを提供できる組織を目指しています。
プロフェッショナルであることの追求と成長を続け、社会に貢献する
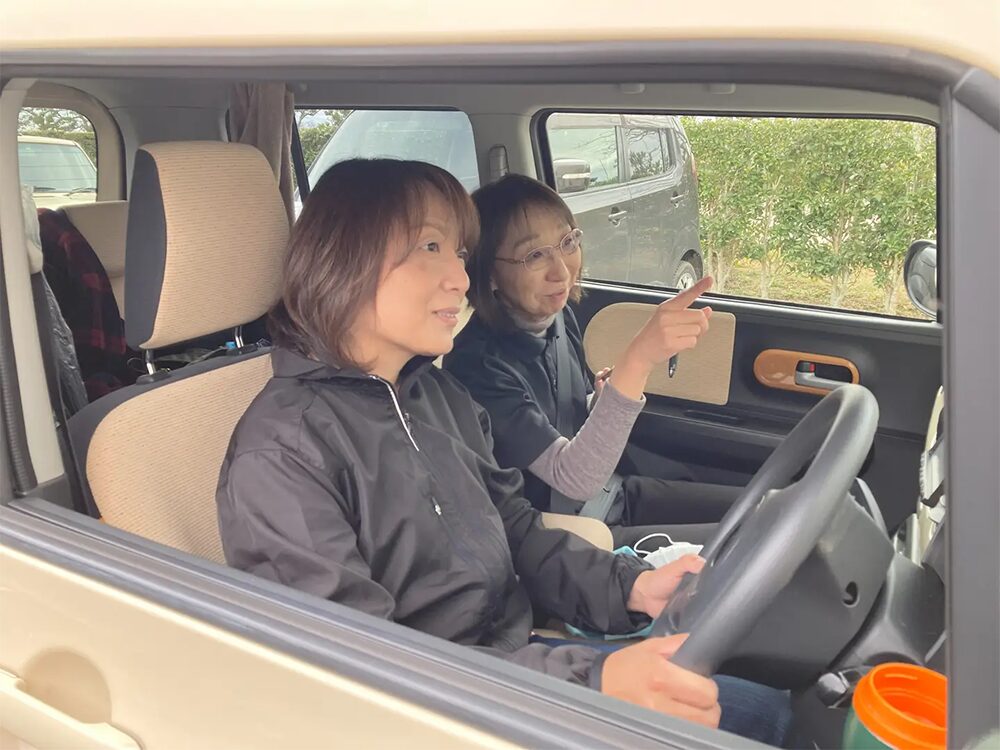
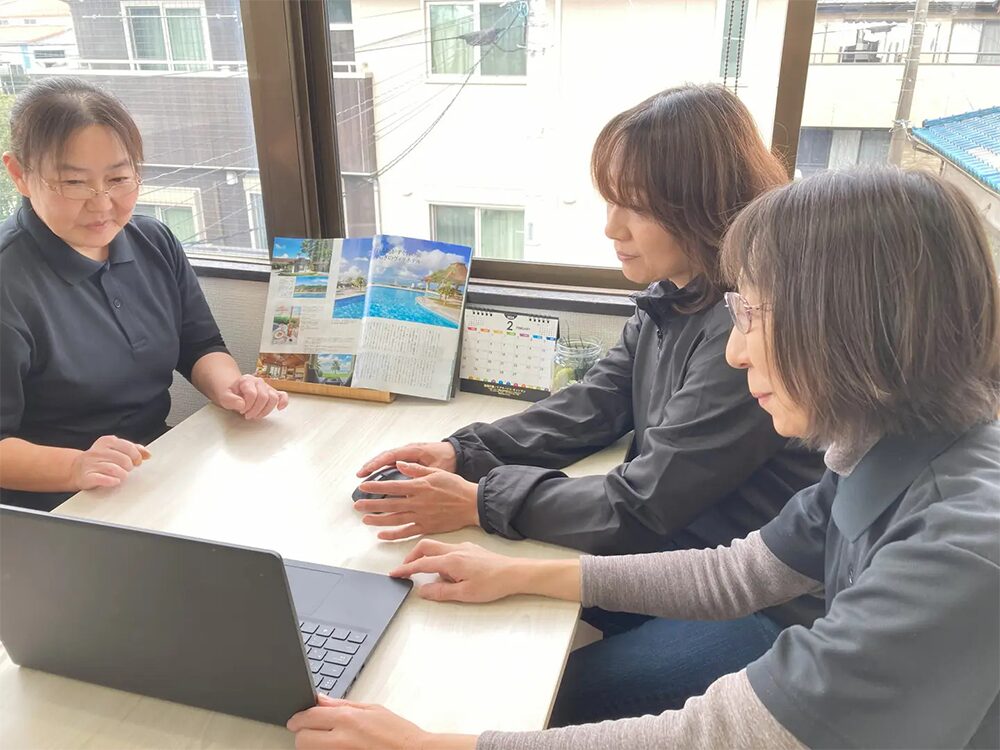
現在、日本は少子高齢化・人口減少等の時代を迎えています。また、日本の中央年齢は45.9歳と世界でも1、2を争うトップクラスの高齢化社会の国となっております。今後の高齢化に伴い医療・介護の需要が増大する傍ら、これらのサービスを支える従事者が不足することで、質の高い医療・介護サービスの提供が難しくなると懸念されます。
その中で私たちはこの社会問題を少しでも解決出来るように取り組んでいく必要があると考えております。
私たちが出来る事から始め、そして1歩ずつ質の高いケアを提供できるような組織にする事を目標として掲げていきます。そして、質の高い介護サービスを継続的に享受でき、人々が安心して暮らせていける未来の実現に向けて、私たちはこれからも、高齢社会の課題解決に挑み続けていきます。
代表取締役社長 橋田 義能


| 企業名 | 株式会社ottoman |
| 代表者名 | 橋田 義能 |
| 本店所在地 | 〒289-1324 千葉県山武市殿台264-6 小川ビル2F |
| 事業内容 | 福祉事業 |
| 資本金 | 200万円 |
| 電話番号 | 0475-86-7410 |
| FAX | 0475-86-7409 | 営業時間 | 8:30-17:30 | 定休日 | 土・日・年末年始(12/30-1/3) |
| 取引銀行 | 千葉銀行・千葉信用金庫・ゆうちょ銀行 |
| 取引会社 | 株式会社アーチ・コミュニケーションズ 株式会社カナミックネットワーク 株式会社wiz LOVES COMPANY 株式会社 オートサービス戸田 株式会社ユニマットライフ セコム株式会社 インターリハ株式会社 株式会社 KRC リフラット株式会社 幸商事株式会社 |

オットマン事務所の雰囲気です。

介護ソフト練習会中の雰囲気です。

オットマンのユニフォームです。

オットマンのエプロンです。
ケアサービス オットマン
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
高齢者虐待防止の担当者は、管理者とする。
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和6年3月1日より施行する。
ケアサービス オットマン
身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。
原則として、身体拘束及びその他の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を禁止とする。
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に行う。
利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。
身体拘束等が一時的であること。
※ただし、肢体不自由、特に体幹機能障害がある利用者が、残存機能を活かせるよう、安定した着座位姿勢を保持するための工夫の結果として、ベルト類を装着して身体を固定する行為は「やむを得ない身体拘束等」ではなく、その行為を行わないことがかえって虐待に該当するため、留意が必要である。
身体拘束等を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことを取組む。
本指針は公表し、利用者等からの閲覧の求めには速やかに応ずる。
身体拘束の廃止に向けて身体拘束等適正化委員会を設置し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
なお「虐待防止委員会」と同時に開催することもできるものとする。
管理者、現場責任者(サービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者)、従業者委員会は上記構成員をもって構成するほか、必要に応じてその他職種職員を参加させることができることとする。
※外部の有識者(第三者・専門家)を加えることも可。
本人又は他利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合は、以下の手順をふまえて行うこととする。
利用中の経過から緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は、身体拘束等適正化委員会において実施件数の確認と身体拘束等をやむを得ず実施している場合(解除も含む)については協議検討し、議事録に残す。
身体拘束等の廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、多職種協働を基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応する。
身体拘束廃止・適正化の検討に係る全体責任者
支援に関わる全ての職員に対して、身体拘束等廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員研修を行う。
附 則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。